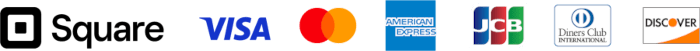遺産分割の前提となる不当利得返還請求訴訟
東京地裁平成22年7月13日
第三 当裁判所の判断
一 争点(1)の本件贈与契約の効力及び本件贈与契約書の偽造の有無について
(1) 原告らは、死因贈与契約である本件第一契約及び本件第二契約の無効確認を求めており、これは、過去の法律関係の確認を求める請求である。
しかし、死因贈与は、遺贈に類似した性質を有するところ(民法五五四条参照)、遺言の無効確認の訴えは、その遺言が有効であるとすれば、それから生ずべき現在の特定の法律関係が存在しないことの確認を求めるものと解される場合で、原告がこのような確認を求めるにつき法律上の利益を有するときは、適法と解すべきであり(最高裁昭和四七年二月一五日第三小法廷判決・民集二六巻一号三〇頁参照)、死因贈与契約についても、上記の要件を満たす場合には、その無効確認を求める訴えは適法と解すべきである。そして、前記第二の一の争いのない事実等、及び第二の二の各項の原告らの主張を考慮すれば、本件第一契約及び本件第二契約の無効確認の訴えは、確認の利益があり、適法と認めるのが相当である。
(2) 《証拠略》によれば、次の事実が認められる。
ア 被告及びその妻は、平成一九年九月ころ、池袋公証役場に行き、公証人前島勝三(以下「前島公証人」という。)に対し、負担付死因贈与契約作成を依頼した。その後、被告らは、前島公証人に対し、贈与契約の内容を伝え、同公証人は、これを基に負担付死因贈与契約書の案を作成し、被告に交付した。
イ 同年一一月一四日、太郎は、肺炎により丁原病院に入院した。入院の手続は被告が行った。
ウ 太郎は、丁原病院に入院した同年一一月一四日から同年一二月末ころにかけて、オムツ内に失禁しながら本人はそれを認識しなかったり、警察を呼びたい旨述べたり、家に帰ると述べて興奮しズボンを脱いだり、病院内の下膳台の残飯やお茶台の中にある茶葉を口にしたり、会話のつじつまが合わなかったり、自分の居場所や日時を理解していなかったりすることがあった。しかし、他方で、看護師から、夜なので寝るように指示され、納得し臥位に戻ったり、看護師から痛いか、苦しいかなどと問われ、痛くない、苦しくないなどと答えるなど、看護師等からの問いかけを理解した上で的確な返答や対応をしているときもあり、太郎との意思の疎通が可能である時と困難な時があった。
エ 太郎は、同年一一月一四日の丁原病院入院時、豊島区長から要介護一の判定を受けていたが、同年一二月一八日、要介護二に要介護状態区分が変更された。
オ 同年一一月下旬ころ、被告は、前島公証人に対し、負担付死因贈与契約の公正証書作成のために、太郎が入院している丁原病院に来るように依頼した。前島公証人は、同年一二月三日、同病院を訪れ、同病院内の食堂において、太郎、被告及びその妻、並びに前島公証人に同行した池袋公証役場の事務員の同席の下、契約内容等を確認した後、太郎に署名押印させるなどして、本件公正証書を作成した。前島公証人が太郎に会うのはこのときが最初であった。
カ 同年一二月一四日、戊田医師は、太郎に関し、介護老人保健施設宛の診療情報提供書を作成し、診断名として、①肝硬変(アルコール性)、②肝がん、③糖尿病、④左胸水、⑤認知症と記載した。認知症の治療経過、治療方針としては、セレネース、睡眠剤により治療していると記載した。さらに、「理解および記憶」の欄では、短期記憶に問題あり、認知能力はいくらか困難、伝達能力はいくらか困難の箇所にチェックを付した。
(3) 本件贈与契約の効力について
ア 太郎の意思能力の有無について
原告らは、太郎が、本件贈与契約締結当時、認知症であり、意思能力がなかったと主張し、かかる主張に沿う原告秋夫の陳述書及び原告夏夫の陳述書を提出するとともに、各原告の本人尋問において上記主張に沿う供述をする。
確かに、前記(2)ウで認定したとおり、丁原病院入院後、太郎には通常人には見られないような言動があったことが認められるところであり、戊田医師が平成一九年一二月一四日付けで作成した、太郎に関する診療情報提供書にも、診断名に認知症との記載が存在する。
しかし、戊田医師は、その証人尋問において、太郎の入院中は、毎日同人を診察していたが、太郎は、同医師が話しかければ大体は何かしらの返答が来るが、病気が悪化しているときは意識がもうろうとして返答がないこともあったとか、相手の話を理解して会話が成り立つときもあれば、相手の話を理解することができないときもあるという波のある状態であったと供述する。この供述を前提とすれば、戊田医師は太郎を認知症と判断していたものの、これをもって太郎が常に意思能力のない状態であったとは認められない。
なお、前記(2)エで認定したとおり、太郎は、丁原病院入院時には要介護度一と判定され、同年一二月一八日には要介護度二に変更されたが、《証拠略》によれば、要介護度は認知の能力のみならず身体能力も併せて判断することが認められ、要介護度一や二と認定された者が、常に意思能力を欠く状態にあるとは認められない。
また、《証拠略》によれば、前島公証人は、本件公正証書作成に際し、太郎の意思能力に問題がないことを確認した上で作成にとりかかったこと、太郎は、本件公正証書の作成の最中に、対象物件の住居表示と登記簿上の記載の相違について指摘したり、押印する印鑑が実印かどうかを気にしていたりしたことが認められる。
さらに、《証拠略》によれば、本件公正証書が作成された日の二日後である平成一九年一二月五日付けの本件贈与契約書には、本件公正証書と同一の太郎名の印影が存在していることが認められ、上記契約書が平成一九年一二月五日より後に作成されたことを窺わせる事実を認めるに足りる証拠はない。なお、本件贈与契約書には、公証人による平成二〇年一月二五日の確定日付が存在するが、これによって直ちに同日ころに本件贈与契約書が作成されたとまでは認められない。
そして、原告秋夫は、その本人尋問において、太郎が何の病気で入院したか知らない旨供述しており、この供述に照らせば、同原告が定期的に太郎を見舞いに丁原病院を訪れ、太郎の状態を確認したのかについては疑問があり、太郎の病状に関する原告秋夫の前記陳述ないし本人尋問における供述は直ちに信用することができない。
以上の事情を総合すれば、本件第一契約締結当時、及び本件第二契約締結当時のいずれにおいても、太郎に意思能力がなかったと認めることはできない。
イ 原告らは、花子の死亡の前後を通じて、被告と太郎はほぼ絶縁状態であり、被告は、太郎の実家にほとんど行かず、太郎に対して暴言を吐くなどしていたのであり、太郎が被告に対してその財産を贈与する動機がない旨主張する。
確かに、花子の日記によれば、花子が生前、被告と太郎の仲を不安に思っていたことが認められるものの、それだけで被告と太郎が絶縁状態にあったと認めることはできず、また、花子が死亡した後において両者の仲が悪かったと認めるに足りる証拠もない。
《証拠略》によれば、被告が太郎の入院のための手続及びその医療費の支払行為を行ったこと、被告夫妻が太郎の入院中の協力者として病院から認識されていたこと、太郎の入院中、被告及びその妻は数回見舞いに行き、同妻と看護師との間において、被告の妻は太郎の入院前から、太郎が事故などを起こさないように注意を払って行動を見ており、また、太郎の入院中に、太郎が退院後にどこで暮らすかということなどについて話し合いがなされていることが認められる。これらの事実からすれば、少なくとも太郎が平成一九年一一月一四日に丁原病院に入院した以降、被告と太郎が絶縁状態であったとは認められず、太郎が被告に対して財産を贈与する動機がなかったとまでは認められない。したがって、原告らの前記主張は採用することができない。
ウ 原告らは、本件公正証書、本件贈与契約書を含めた複数の書面に存在する太郎の署名の筆跡がそれぞれ大きく異なっていることは、太郎の精神状態が異常であったことを示す旨主張し、これに沿う証拠として筆跡の鑑定書を提出する。
しかし、上記鑑定書で取り扱われている太郎の署名は、手帳から抜粋された太郎の直筆とされているもの以外は、太郎が丁原病院に入院中に記載したものと認められるところ、《証拠略》によれば、太郎は、丁原病院入院中、身体を拘束されていた時期もあることが認められる。そして、入院中のベッドの上であったり、身体を拘束されているなど、太郎が署名をした際の姿勢によって、筆跡に違いが出ることも十分考えられるところであり、複数の署名の筆跡が異なることをもって、太郎の精神状態が異常であったとか、太郎が意思能力を欠いていたとまでは認めることができない。
また、原告らは、本件贈与契約書の太郎の署名が偽造であると主張する。しかし、本件贈与契約書の太郎の署名と、本件公正証書の太郎の署名を対照すると、筆跡が似ているということができ、前記(2)オで認定した事実によれば、本件公正証書の太郎の署名は、太郎によって書かれたものであるから、本件贈与契約書の太郎の署名も、太郎によって書かれたものと認めることができる。そして、前記鑑定書も、本件贈与契約書の太郎の署名が太郎によって書かれたものではないとの意見は述べていないことを併せ考慮すれば、本件贈与契約書の太郎の署名が偽造であるとは認められない。したがって、原告らの前記主張は採用することができない。
エ 原告らは、太郎及び花子が、生前、原告らに対し、その遺産を子らに平等に相続させる旨述べていたと主張し、この主張に沿う証拠として花子の平成一八年三月五日の日記を提出する。
同証拠によれば、花子が生前、原告ら及び被告に花子の遺産を平等に相続させる希望を有していたことが認められるものの、花子の死後、太郎が自らの遺産を子らに平等に相続させる意思を有していたと認めるに足りる証拠はない。
オ 以上によれば、本件贈与契約はいずれも有効に成立したということができる