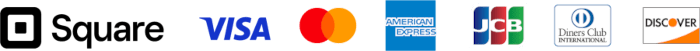「終わらない成年後見」から「終わることができる成年後見」へ
「終わらない成年後見」から、「終わることができる成年後見」へ
――法制審中間試案と任意後見・民事信託のゆくえ
成年後見制度は、高齢者などが認知症等で判断能力が継続的に低下した方を法的に支援する制度です。「法定後見」と「任意後見」は同じ後見制度に属しますが、その成り立ちも、使われ方も、かなり違います。
法定後見は、本人の判断能力が既に不十分になってから、親族や市町村長などの申立てにより家庭裁判所が後見人を選任するのが典型です。現実には、後見人は全く面識のない弁護士等の専門家が選任されることも多く、預金の解約など財産管理を行う必要性から開始されます。本人に異議権はなく、「いつの間にか制度の中に入っていた」という形になりがちです。成年後見人に関するご不満もしばしば聞きます。
これに対し、任意後見は、本人に判断能力がある段階で、将来の自分の老後等に備えて、自分で後見人候補者と公正証書で契約を締結する仕組みです。私は、主として単身者が、自らの将来に備え、自分の希望通りの老後を実現する手段として利用している例を想定します。このため、任意後見契約だけではなく、見守り契約、財産管理委任契約、死後事務委任契約など、任意後見に架橋する契約をセットで締結しておく実務も広がりつつあります。
もっとも、数字を見ると、実態はかなり偏っています。法定後見が全体の約9割を占め、任意後見は1%程度にとどまります。
その背景には、成年後見制度そのものが抱える構造的な問題があります。後見人の包括的な同意権・代理権が強大すぎて障害者権利条約に適合しないと批判されていること、いったん開始すると実質的に死亡するまで終了できないこと、開始した途端に財産が「半分凍結」のような状態になり、柔軟な資産運用が難しくなること…。
こうしたことから、最近では、成年後見を避け、民事信託(家族信託)など、より機動性の高い手段を検討する動きも広がっています。そして、その一方で、成年後見制度そのものについても改正の議論が本格化している、というのがいまの風景です。
1 「終わらない成年後見」という硬直性
この「終わらない」「強すぎる」成年後見の構造に、立法レベルでメスを入れようとするのが、令和7年6月10日に公表された法制審議会民法(成年後見等関係)部会の「中間試案」です。もちろん、現在も議論は続いています。
現行の法定後見では、一度開始されると、原則として本人の事理弁識能力が回復しない限り、制度を終わらせることができません。
遺産分割や不動産売却など、利用のきっかけとなった課題が解決しても、介護や生活支援のネットワークが整っても、「判断能力が回復していない」という一点で、制度は半ば惰性的に続いていきます。そのあいだ、成年後見人の代理権・取消権は広範に及び、本人の財布と契約の自由は、必要以上に絞り込まれてしまうこともある。
中間試案がまず正面から捉えたのは、この「硬直性」です。
試案はおおまかに、次のような方向性を示しています。
利用動機となった課題(たとえば遺産分割)が解決し、保護の必要性・補充性が消滅した場合には、判断能力の回復がなくても終了できるようにすること
一定の「期間」や見直しのタイミングを制度の中に組み込むこと
本人の状況変化に応じて、後見人の交代をより柔軟に認めること
つまり、「一度入ったら事実上出られない制度」から、「必要なときに必要なだけ使い、状況に応じてやめることができる制度」に近づけようとしているわけです。これは、任意後見や民事信託を検討してきた実務からすると、「ようやく制度側が現場に追いついてきた」と感じられる部分でもあります。
2 抜本改正ではなく、「複線的・漸進的」な動き
もっとも、今回の見直しは、成年後見制度をゼロから作り直す「革命」ではありません。
中間試案では、
現行の後見・保佐・補助という三類型を修正しつつ維持する案(甲案)
個々の行為ごとに、必要な範囲で代理権・取消権を付与する新しいタイプの法定後見を設ける案(乙案)
が並列的に提示され、どこまで踏み込むかは、なお議論の途上です。
個人的には、乙案をベースラインにカスタマイズしてゆくのが現実的と考えています。
背景には、障害者権利条約や国連障害者権利委員会の勧告に対する「距離感」の問題があります。
一方には、「条約が求める方向にできるだけ忠実に近づけるべきだ」という立場があり、もう一方には、「条約は尊重しつつも、日本の民法の基本構造(私的自治・取引安全)との調和の中で受け止めるべきだ」という慎重論があります。しかし、大人である高齢者の自己決定権を完全に制限するのは相当ではありません。
自律の保障やインクルージョンといった新しい理念を、民法の条文レベルまでどこまで書き込むか。成年後見をどこまで「例外的なラストリゾート」に位置づけるのか。それをめぐる綱引きのなかで、中間試案は、「いきなり全部変える」のではなく、「複線的・漸進的に変えていく」方向を採りつつあるように見えます。しかし、条約適合的に行われるべきようにも思われます。
3 あえて「周辺」に置かれた論点たち
興味深いのは、「本当は重いはずなのに、今回はあえて周辺に追いやられている」論点群です。
第一は、「身体障害により意思疎通が著しく困難な人」を成年後見制度の対象に含めるかどうかという問題です。
意思形成には支障がないが、表現・伝達に支障があるケースを、精神上の障害と同じ器に入れてしまってよいのか。比較法的には対象に含める例もありますが、「民法の成年後見で担うべきなのか、それとも福祉の支援体系で受け止めるべきなのか」という根本的な問いが、まだ整理しきれていません。中間試案では「今後の検討課題」として第8章の「その他」に位置づけられています。
第二は、医療行為への同意権の問題です。
医療・介護の現場では、「後見人さんがいるなら同意してほしい」と求められる場面が少なくありません。しかし、成年後見人は財産管理権が中心です。包括的な医療同意権を法定するとなれば、本人の身体への介入を法的に正当化する仕組みをどう作るか、極めて重い立法判断になります。
中間試案は、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)やチーム医療の流れを踏まえつつ、「家庭裁判所が医的侵襲への包括同意権を付与できる」とまで書き込むことには慎重な姿勢を示しています。ここでも「必要な論点であることは誰も否定しないが、成年後見の枠に全部押し込むべきか」はあえて未整理のまま、次のラウンドに送られました。
これらはいずれも、制度の価値観そのものに踏み込むテーマですが、今回の見直しでは、「まずは終わらない制度・強すぎる制度をどう緩めるか」というところにターゲットを絞った、とも言えます。
4 任意後見・民事信託との関係で、私たちが考えるべきこと
では、この中間試案を、任意後見や民事信託を視野に入れている人たちは、どう受け止めればよいのでしょうか。
一つは、「終わることができる成年後見」という発想を、老後のライフプランにどう位置づけるか、という問いです。
——包括的な法定後見一本に頼るのか。
——任意後見契約・見守り契約・財産管理委任・死後事務委任を組み合わせて、自分で選んだ人に役割を託すのか。
——そのうえで、どうしても必要な局面では法定後見を短期・限定的に使うのか。
民事信託も含めて言えば、「全部後見」「全部信託」という二択ではなく、「どの段階で、どのリスクを、どの手段でカバーするのか」を設計する発想が必要になります。
その意味で、「終わらない成年後見」から「終わることができる成年後見」への方向転換は、任意後見・民事信託と対立するというより、「使い分け」の可能性を広げる改正になるはずです。
もう一つは、成年後見制度の目的に「相手方保護」がどのように位置づけられるか、という視点です。
取消権や無権限の行為が頻発すれば、金融機関や取引当事者は萎縮し、事実上、本人の生活が不便になってしまう。他方で、「取引安全」を過度に優先すれば、「本人のための制度」という成年後見のアイデンティティが揺らぎます。
中間試案はここでも明快な答えを出してはいませんが、「本人の自律」と「相手方の保護」を同じテーブルに乗せて議論する必要があることだけは、はっきり示したと言えます。
5 「制度に入る前」と「入ってから」をどうつなぐか
最後に、任意後見・法定後見・民事信託を一歩引いて眺めてみると、問いはとてもシンプルになります。
「判断能力があるうちに、どこまで自分で決めておくか」
「判断能力が低下した後、どこまで制度に委ねるか」
任意後見契約は前者を強化するツールであり、法定後見は後者を支えるツールです。民事信託はその間を柔らかくつなぐバッファのような役割を果たし得ます。
中間試案が目指しているのは、この三者の関係を、少なくとも「後見に入ったら最後」という一方通行からは、そっと引き離すことです。
制度の細部がどう決まるかは、これからのパブリックコメントと立法作業次第です。
しかし、実務家として・当事者として、いまから準備しておくべきことは明確です。
「終わらない成年後見」しか選択肢がない、という前提をいったん疑うこと
任意後見・見守り契約・財産管理委任・死後事務委任・民事信託といったツールを、老後の設計図のどこに置くか考えてみること
そして、どうしても法定後見が必要になったときには、「どこまで」「どのくらいの期間」制度に委ねるかを意識することがあります。つまり、重要な財産の管理が終われば、成年後見人を維持し続ける必要性があるかは分かりません。
成年後見制度の見直しは、条約適合や理論の話に見えますが、突き詰めれば、「自分の老後の主導権をどこまで自分で握るか」という、とても個人的なテーマでもあります。
「終わることができる成年後見」という発想に慣れておくこと。それが、これからの私たちにとっての、最初の宿題なのだろうと思います。